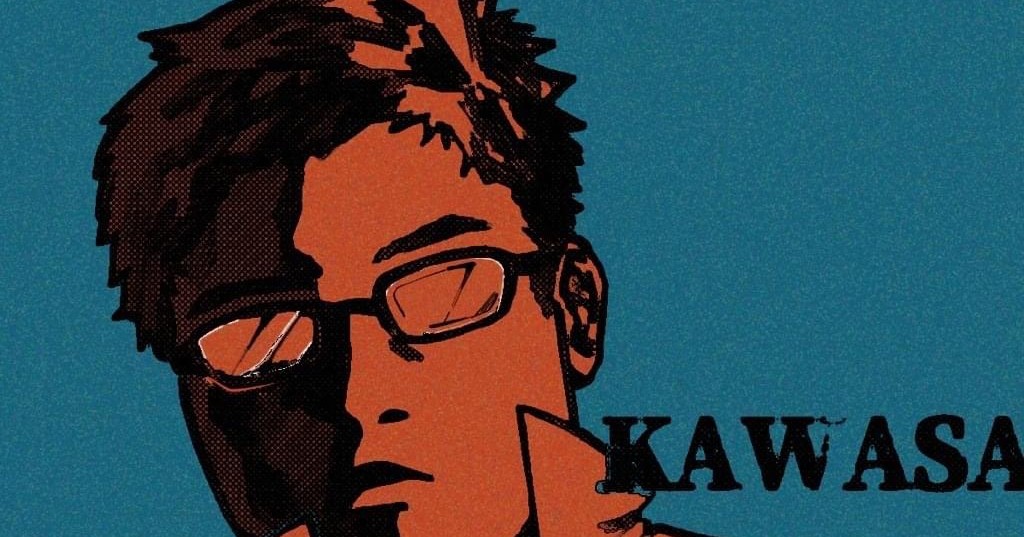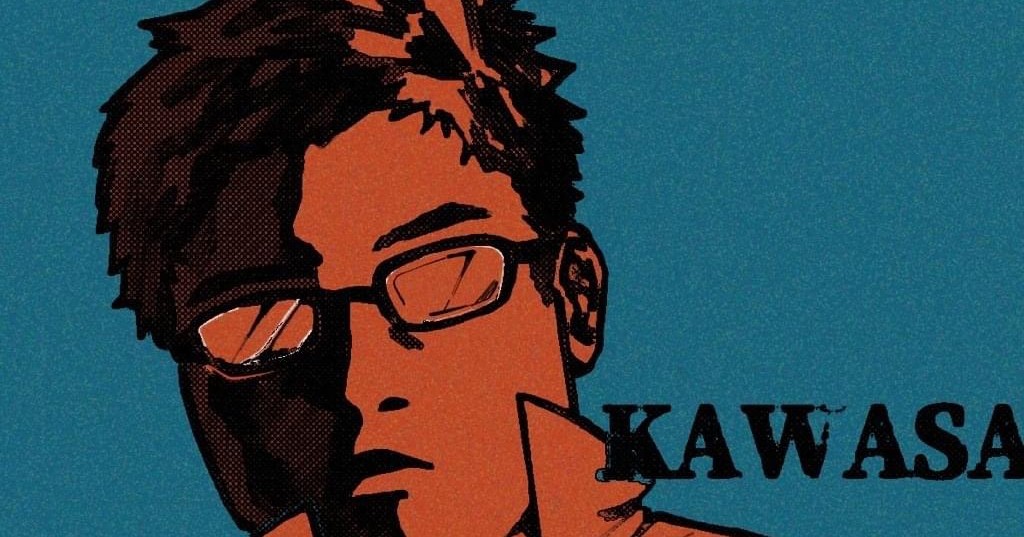乳幼児健診は誰のため? -これからの5歳児健診を考える その1-
乳幼児健診の展開から「5歳児健診」を考える
2023年から母子保健医療対策総合支援事業の一環として子ども家庭庁が5歳児健診の全国展開を推し進めていますが、実は2000年代頃より一部の自治体ではすでに先行実施されていました。当時から「就学前に見出すことが難しい発達障害特性の早期検出」が目標として掲げられていたように思います。本来、こどもと養育者が安心して日々を送るためのサービスである乳幼児健診全体について少し振返りつつ問題を明らかにしていきたいと思います。
【乳幼児健診を理解する・乳幼児健診とは?-「見出す」から「支える」へ-】
こどもの成長や発達の状況を早期に把握し必要に応じて医療や支援につなぐことを目的としたものです。決して障害があるこどもを見出すためだけでもなければ、それがゴールというわけでもありません
母子保健法に基づき、実際一歳半健診と三歳児健診が全ての自治体で義務として実施されています。乳幼児健診の一番の目標は「養育者とこどもが安心安全で日々の生活を送ること」であり、そのためにできる手段として医療や福祉を提供するきっかけにすることにあります。ただ、乳幼児健診の目的は時代に応じて少しずつその色合いを変えています。ここで「今我々の目の前にある問題」を解決するためにも少し現在に至るまでの流れをまず振り返ってみたいと思います。
命を守るための制度として-草創期-
もともとこの制度の起源をたどると、1947年の児童福祉法によって乳幼児健診が制度化(当時は任意)されました。戦後、未だ乳幼児死亡率の高さやよる感染症の蔓延といった深刻な公衆衛生上の課題に対処するため、1965年には母子保健法が制定に繋がります。一歳半健診や三歳健診が義務化されたのもこの時です(1965年当時も乳幼児死亡率は1.8%と決して低くなく、幼児死亡率も現在の10倍以上)。つまり設立当初は母子の命を守る事が第一目標の制度であったといえます
集団維持のための早期発見の手段として-進展期-
70年代以降高度経済成長に伴い乳幼児死亡率は低下して行きます。社会状況の変化に伴って生命維持や健康から必然的に養育者の焦点が「発達や発育」といった視点にむくようになりました。それに合わせて健診の持つ意味も変化を見せます。時代はちょうど第二次ベビーブームの世代であり子どもたちの教育に世間の注目が集まりはじめた時期でもあります(かくいう私もこの世代です)。こういった流れに応じて幼児教育や育児書が医学の手を離れて一般書として大きく流行りだしたのもこの時期です。年間出生数が200万人を超えていた時代、政策的な影響も強くあり、子育てや教育は画一的な母性中心主義の時代でした。当然、この時期の健診も典型発達とは異なる児童を「見出す」視点が中心となっていました。当時の社会的風潮(教育界において色濃く)が標準的な基準からの逸脱=それこそが問題であると捉えていたことを色濃く反映するものです(もちろん私はまったく納得していませんが)。保険者が行政の役割は「リスクの把握と管理」が中心であり、その地域に応じたこども全体の健全な育ちの在り方を考え支えるという発想はなく、「(当時の集団を揺るがすと考えられていた)リスクを効率的に発見し処置に繋げる」ことこそがその時代を維持する上で重要であると考えられていた時代とも言えます。
勿論のことこの当時は狭い意味での「医学的視点」中心であり「発達の揺らぎ」や環境の影響は軽視(場合によってはほとんど無視)され、行動上の問題は「親のしつけ」で片づけられ、ことばの遅れも「親の育て方」の問題と片付けられていました。「親がしっかりすればこどもは育つ」という家庭責任主義が幅をきかせていた時代と言えます(未だに現在もその名残が残っているのは残念な限りです)。
当時、育児不安や親の困り感は家庭で解決すべきものという考え方であり、保護者支援という概念自体が希薄だったわけです。