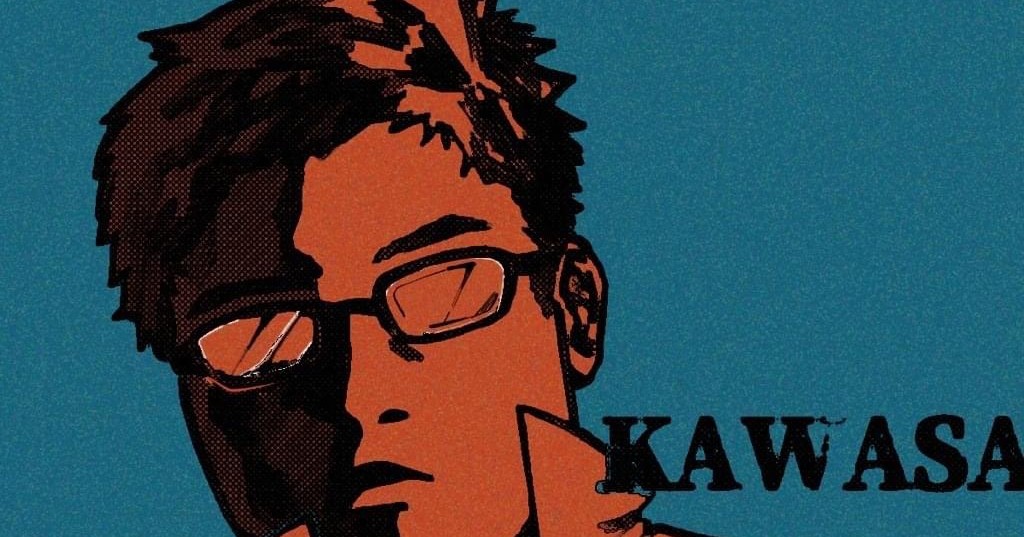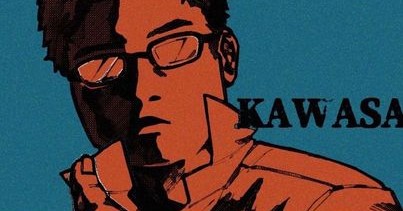誤解だらけのワーキングメモリ (WM)―何かあると
ワーキングメモリの実態
皆さんは「ワーキングメモリ」と聞いて、何を思い浮かべますか?
「学習のときに使う記憶」と答える人もいれば、「短期記憶と長期記憶の間にある記憶」と説明する人もいます。さらに、「パソコンに例えるとRAMだね」と言われることも少なくありません。
これらのイメージは部分的には正しいのですが、実際の定義からするとずれていたり、その一部だけを切り取った理解だったりします。現在の研究で捉えられているワーキングメモリは、単なる容量や場所ではなく、学習に必要な複数のコンポーネントに支えられたシステムです。言い換えれば、ワーキングメモリは「短期記憶」ではなく「ワーキングメモリ・システム」として理解する必要があるのです。
その後、Baddeley (2000) はワーキングメモリを複数の構成要素からなるモデルとして整理しました。すなわち・・・
〇中央実行系(central executive):注意や制御を司る中枢的な働き
〇音韻ループ(phonological loop):言語情報の保持と操作
〇視空間スケッチパッド(visuospatial sketchpad):位置や形など視空間情報の保持と操作
〇エピソディック・バッファ(episodic buffer):異なる形式の情報を統合する場(後で追加)
という4つのコンポーネントから成るとされます。
理解を深めるために、これらを教室のグループ学習にたとえると、イメージがわかりやすいでしょう。中央実行系は全体の進行を管理する「先生役」、音韻ループは音読や暗唱を担当する「読み上げ係」、視空間スケッチパッドは図や表を黒板に描く「図解係」、そしてエピソディック・バッファはそれらの情報をノートに整理して全体像をまとめる「まとめ役」にあたります。
そして驚くべきことに、これらの作業は教室の中のグループ一人ひとりの活動ではなく、一人の頭の中で同時に作動しているのです。だからこそ私たちは、学習や思考を進めながら情報を保持し、必要に応じて操作することができます。さらに、この働き全体を意識して調整するのが「メタ認知」の役割です。いわば、学習を進める自分自身をもう一人の視点から見守る「監督」のような存在であり、ワーキングメモリと切っても切り離せない関係にあります。